私たちは日常生活や職場で、「コミュニケーション能力」が高いとか低いといった話を耳にします。そこで本当に「コミュニケーション能力」を理解できているのか?何をもって高い・低いと判断するのでしょうかと疑問になりました。私の場合は「あ〜勘違い」でした。
1.コミュニケーション能力とは?
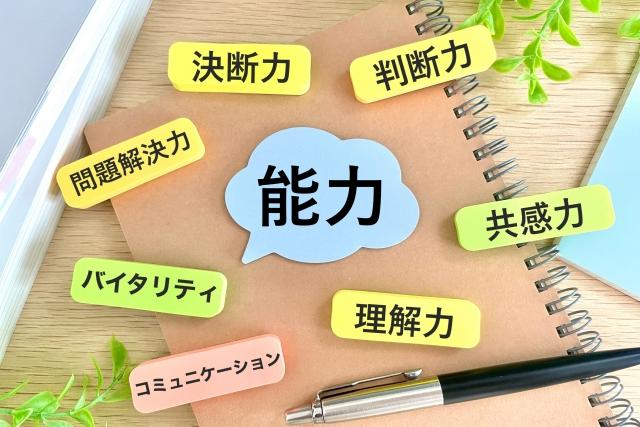
■コミュニケーション能力とは・・
単に話が上手なことだけではなく、相手の意図を理解し、自分の意図を適切に伝え、良好な人間関係を築く総合的な力。
では、高い人と低い人の特徴の比較や判断基準を整理してみよう。
【コミュニケーション能力の定義】
コミュニケーション能力は大きく分けると以下の4つの力で構成されると言われています。
伝える力》
自分の意見や考えを相手に分かりやすく伝える力。文章力や話し方だけでなく、タイミングや態度、声のトーンなども含まれます。
聞く力》
相手の話を注意深く聞き、正しく理解する力。単に耳で聞くのではなく、相手の言外の気持ちや状況を読み取る「傾聴力」も重要です。
深める力》
会話の内容を掘り下げ、関係性を深める力。質問力や共感力を活かして、相手との信頼関係を築くことができます。
場を楽しむ力》
場の雰囲気を読み、場を活性化させる力。冗談や雑談、場の空気を和ませる力が含まれます。
これらの力のバランスが取れている人は、職場や家庭、友人関係でも円滑なコミュニケーションが可能ということですね。
2.コミュニケーション能力の高い人と低い人の比較

では、実際に高い人と低い人はどのように異なるのでしょうか。
| 項目 | コミュニケーション能力が高い人 | コミュニケーション能力が低い人 |
|
話す内容 |
相手に分かりやすく整理して伝える | 自分の言いたいことだけ話す、論点が不明瞭 |
|
聞き方 |
相手の話を最後まで聞き、理解を確認する | 話を遮る、聞き流す、自己中心的 |
|
関係性 |
信頼関係を築き、協力的な関係を作る | 信頼関係が築けず、孤立しやすい |
|
場の雰囲気 |
場を明るくし、参加者全員が話しやすい雰囲気を作る | 場が重くなる、会話が途切れやすい |
|
問題解決 |
意見を交換しながら建設的に解決策を探る | 意見の押し付けや無関心で解決が難しい |
例えば・・
職場ですと、会議で意見を求められた時、高い人は論点を整理して簡潔に伝えつつ、他人の意見を受け入れる姿勢があります。
低い人は自分の主張だけを話し、相手の意見を遮ることがあります。
この差は、信頼関係や生産性にも直結します。
■高い人と低い人の判断基準
コミュニケーション能力を判断する際には、次のような点が基準となります。
相手に理解されるか》
話の内容が相手に正確に伝わるかどうか。分かりやすい言葉で話しているか、誤解を生まないかが重要です。
相手の意図を理解できるか》
相手の立場や感情を考慮して、適切な反応や対応ができるか。傾聴力や共感力がここで試されますね。
信頼関係を築けるか》
仕事やプライベートで、長期的に協力関係を維持できるかどうか。高い人は関係性を優先して行動します。
場を活かせるか》
集団や会議の雰囲気を壊さず、円滑にコミュニケーションを進められるか。単に自分が話すだけでなく、場全体を意識できるかがポイントです。
3.「コミュニケーション能力」は重要では無い!

私の勘違い・・注意点として
「コミュニケション能力」は重要では無い!と思っている節がありました。
なので、私は「コミュニケーション能力」は無いです。
それは、大きな勘違いでした。調べてみると業務においては低いよりは高い方が良い!ということに気付かされました。
注意すべきは、知識や技術が高くても、コミュニケーション能力が低いと信頼関係は築けないということです。
例えば・・
優れた技術者でも自分の主張ばかりを押し通す、聞く力が不足している場合、周囲は協力を避ける傾向があります。
コミュニケーション能力は、単なるスキルではなく、人間関係の潤滑油であり、職場での成果を左右する重要な要素です。
調べてみると・・
そうなんだ・・・と考えさせられました。
人間関係の潤滑油という表現になると、信頼関係が構築された友人・知人が多い方が「コミュニケーション能力が高い人」になるのかな?と考えました。
全ての方々に言えることでも無いかもしれませんし、それぞれ人の価値観には違いがあり、信頼関係が構築された人が複数いることに、メリットがあると考えない方々もいると思いますが・・。
余談ですが・・
以前勤めていた職場で・・経理担当女性は業務的には優秀だと周囲に見られていた方でしたが「プラベートの話は、勤務時間中にしないで下さい」と誰にもキッパリいう人でした。
そして休憩時間には、毎日経済新聞を隅々まで読み込むのが日課で楽しみなようでした。
「変わった人ですね・・」と言われていましたが、経理の仕事、事務作業は完璧な程にきちんとされていました。
人には、価値観の違いもあるのでしょう。業務以外で人と無駄話をすることが嫌いな方でしたね。
私の場合は、「場を楽しむ」が好きで、その場で楽しめれば、後々の交流は少々面倒に感じることが多いのです。
長期的な協力関係は不要に思っていたのかもしれません。(家族最優先でしたので・・)
今回しっかり調べてみて、職場では一つのスキルとして「コミュニケーション能力」を高める為に、少しは努力してみることも、課題としては必要なのかもしれないな〜と思いました。
4.まとめ
コミュニケーション能力は「話す力」「聞く力」「深める力」「場を楽しむ力」の4つの要素で構成されます。
高い人は相手を尊重し、関係性を重視しながら自分の意見を適切に伝えられるのに対し、低い人は自分本位の話し方や傾聴不足で信頼関係を築くのが難しい傾向があります。
判断基準としては「理解される力」「相手を理解する力」「信頼関係を築けるか」「場を活かせるか」がポイントです。
職場や家庭、日常生活での良好な人間関係を築くためには、これらの能力を意識的に高めることが必要だということに気付かされました。
私と同じように、勘違いされている方がいれば参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
大阪で看板製作・施工は看板屋 ㈱ラグレスまで・・他府県でも対応可能です。
まずは、御見積り・お問い合わせからでもお気軽に・・・・・
