ある日の雑談の中で、自身のことを「意見をするのは100年早いと思っています」というスタッフ。思わず拍手する私!!。今の時代に、その言葉を発する若者がいるのか・・と感心してしまいました。時代と共に変わるマインド作りについて探る。
目 次
1.「意見をするのは100年早い!」マインドの特徴
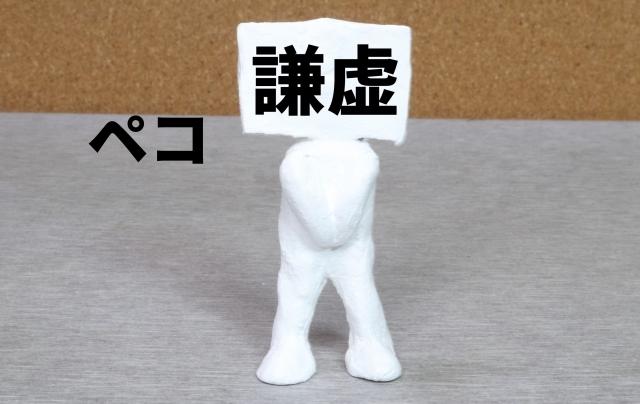
1.単なる消極性ではない思考
この言葉の裏には、単なる消極性ではなく、いくつかの特徴的な思考が隠れていそうです。
■謙虚で学び志向
このタイプの若手は、自分に経験や知識がまだ足りないと自覚しており、安易に意見を出すことを避けます。
まずは学び、理解を深めることを優先するため、反論することは「まだ自分の立場では早すぎる」と判断します。
■組織順応型
先輩や上司の指示を尊重し、まず従うことで信頼を得ようとします。
上下関係を重んじる文化が残る企業や、まだ社会人経験が浅い社員に多く見られる傾向です。
■リスク回避意識
未熟な段階で意見すると失敗や誤解につながる可能性を意識してるのでしょう。
慎重に行動することで、自分の信用や評価を守ろうとする心理が働きます。
2.現代の若手社員における存在状況は?
昔は、上下関係に従順であることが「美徳」とされていました。
現代の社会では、意見を発信できることが価値とされる風潮も強くなっていますね。
SNSやオープンな情報環境の影響で、若者は自分の意見を持ち、発信することに慣れているケースも少なくありません。
それでも、経験が浅い層では慎重さから「今は発言を控える」という行動が残ります。
特に、高度な責任や成果を求められる環境、上下関係が明確で指示命令型の文化では、このマインドが強く現れることもあるようです。
ということは、現代でも「意見をするのは100年早い」と感じる若手は存在していて、これは単なる古風な価値観ではなく、「経験不足・自信不足に基づいた慎重さ」からなのかもしれませんね。
3.周囲の接し方の理想

■挑戦の安全な場を与える
小さな改善提案や判断を任せることで、「自分の意見が組織の役に立つ」という成功体験を積ませることができます。
失敗してもフォローする姿勢を示すことが重要です。
■意見を引き出す質問を投げかける
「この場合、どう考える?」と逆に問いかけることで、自ら考え意見を出す習慣を育てます。
最初は控えめでも、少しずつ発言の機会を増やすことで主体性が芽生えます。
■成長を可視化する
「前はここまでできなかったけど、今はこう改善できたね」と具体的にフィードバックすることで、自信を持たせます。
謙虚さと成長意欲を両立させることが可能です。
■長期的な視点で育成する
反論や意見を控える姿勢は短期的には消極的に見えますが、長期的には学びを重視する姿勢として成長の土台になります。
焦らず段階的に主体性を育てることが大切です。
2.「私がする必要があります?」マインドの意味

1.「私がする必要があります?」は確認思考
けれど、この言葉には単なる確認以上の心理が潜んでいる可能性があるようなのです。
■責任回避の傾向
経験の浅い社員は、まだ業務や組織の仕組みを十分に理解していないことがあります。
そのため、できるだけ負担を避けたい、失敗したくないという心理が働き、「やらなくて済むなら避けたい」という気持ちを言葉にしている場合があります。
■役割認識の曖昧さ
どの作業が自分の担当範囲なのか明確でない場合もあります。
「自分の仕事ではないのでは?」という疑問から発言が出ることが多く、本人は確認のつもりでも、周囲からは責任逃れのように映ることがあります。
■主体性の不足
この発言は、与えられた仕事を自らの判断で進める主体性がまだ育っていないことを示しています。
自分から行動する前に「本当に自分がやるべきか」を問う姿勢は、受け身型マインドの典型例です。
2.現代の若手社員に見られる背景
現代の若手社員は、学校やアルバイト経験を通じて「主体性を求められる環境」に慣れている場合が多い一方で、社会人としての責任や役割を理解するのはまだ途上です。
・経験のない組織での責任
・複数の業務やプロジェクトの並行
・上司や先輩との関係性の把握
など、多くの不安や判断材料が重なります。
その結果、「本当に自分がやるべき仕事なのか」を確認する慎重な行動として、この発言が出ることがあります。
3.周囲の接し方の理想
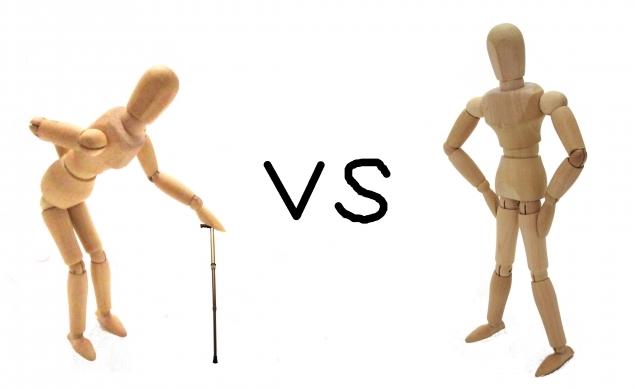
放置せず、適切にフォローしながら主体性を育てることが重要です。
■役割の明確化
「この作業はあなたの担当です」と明確に伝える。
あいまいな指示を避け、責任の範囲を具体的に示すことで、逃げ道をなくします。
■仕事の意義を示す
「この作業を担当することで、チームの進行がスムーズになる」
「この経験は将来のステップにつながる」
意義を伝えることで、受け身ではなく前向きな行動に変えられます。
■小さな成功体験を積ませる
達成できた場合は具体的に褒める。
「自分がやる意味があった」と感じられる体験が、責任感と主体性を育てます。
■段階的に難易度を上げる
最初は簡単な業務から始め、徐々に判断や裁量を与える。
成功体験と少しずつの挑戦の積み重ねで、主体性を強化します。
3. まとめると・・
「反論するのは100年早い」と考える若手社員は、今の時代でも存在します。
その背景には、謙虚さ・経験不足・自信不足があり、必ずしも古い価値観だけではありません。
上司としては、無理に反論させるのではなく、安全な挑戦の場・意見を出す機会・具体的な成長のフィードバックを通して、主体性と発言力を育てることが重要です。
「その作業は私がやる必要がありますか?」は、受け身・責任回避・慎重さの表れ。
上司としては、役割を明確化し、仕事の意義を示し、成功体験と段階的挑戦を積ませることが重要。
この対応により、受け身マインドを主体性と成長志向に変え、将来的な組織貢献につなげることができる。
若手社員はまだ社会人としての土台を作っている段階です。
現代の若手社員のマインドは多様であり、謙虚さを活かし、適切な導きと経験を与え 段階的に成長させる指導こそ、本人のキャリアと組織の未来を両立させる鍵になりそうです。
ありがとうございました。
大阪で看板製作・施工は看板屋 ㈱ラグレスまで・・他府県でも対応可能です。
まずは、御見積り・お問い合わせからでもお気軽に・・・・・
